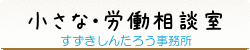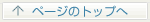少額訴訟に適しない請求と被告側での対応相談室からひとこと
少額訴訟は、制度を悪用されると難易度が上がります
この少額訴訟、筆者自身が独立前に働いていた行政書士事務所への残業代請求で使ったことがあります(別コンテンツ 『おはよう』のない事務所で 参照)。しかし簡単そうで実は怖い、という印象を受けました。
労働相談や役所の無料法律相談で推奨されることも多い少額訴訟ですが、未払い賃金や残業代請求の手段として簡単だから人に勧める、というものではないと考えています。
少額訴訟の最大の長所は、一回の期日で訴訟が終わる制度であることです。あとは当事者尋問について、前もって尋問事項を明らかにしておく必要がない(裁判官の方で、ある程度柔軟に対応してくれることがある)というような、手続きが若干簡略化できていることくらいです。
ところがこうした点については、実際には通常訴訟と同じように準備しておいた方がよいことが多く、さしたるメリットではありません。
少額訴訟の危険性
そして、少額訴訟は法律専門家や法律をもてあそぶのが好きな人を敵に回した場合に悪用されやすい特徴を持っています。一期日で訴訟が終わることさえ、悪用されれば本人訴訟を行う原告に不利な要素になります。
具体的にはウソを書いた答弁書(準備書面)や偽造の証拠を当日になっていきなり提出された場合、それに対応する余裕なく敗訴または不利な和解に追い込まれる可能性が高まります。
一部の法律関係者や素人はこうしたことを平気で行います。
自分で少額訴訟を起こそうとする人は十分な注意が必要です。
また、労働者側が少額訴訟として提訴しても経営者(被告)は何の理由もなく通常訴訟への移行を申し立てることができますから、敵が時間稼ぎを望んだ場合には無力です。
これらの妨害がなくても、一回の期日で自分自身で十分な主張と立証を尽くさなければ(あくまでも裁判なので、自分に有利な事実を主張し証拠づける責任は、裁判官でなく自分自身にあるのだから)請求そのものが通りません。つまり負けます。敵が強かったからではなく味方が弱かった・自滅した、というパターンです。
だからといって訴状提出の際にすべての主張と証拠方法を明らかにしてしまうと、被告側に(こちらの主張と最低限のすりあわせを行った)ウソを出す機会を与えてしまいます。
要は裁判官から見て、口頭弁論期日の1~2時間の間だけ優勢を維持した方が勝つ、少額訴訟はそんな訴訟なのです。
こうした点を前提とすると、少額訴訟は上手に早く終わらせるためにかえって難しくなってしまう訴訟だといえます。もちろん、口頭弁論期日1日の間だけ優勢を維持できれば筆者のように、残業代と賃金の支払い請求訴訟で請求していない解雇予告手当の一部を回収して一気に和解してしまう、という展開も考えられます。
少額訴訟だからといって安易に対処しようとすると、周到に準備してきた対立当事者に手ひどく叩かれる可能性は原告にも被告にもあり、審理が一日で終わってしまう分その危険は大きいと考えるべきです。
少額訴訟と労働審判の比較をされる方へ
『少額訴訟 労働審判 残業代』といったキーワードで検索される方は、おそらく残業代の請求その他の労働紛争で60万円以下の請求を考えていて、しかも迅速な解決を目指しているのだと思います。少額訴訟が1回の期日で終わる制度設計をされていながら、被告側で自由に通常訴訟に移行できる=一期日で終わる可能性をなくすことができるのに対して、労働審判は相手側の意向にかかわらず最大3回の期日で審判が出て終わることになっており、例外はほとんどありません。
労働審判の場合、請求額に制限がないことと残業代の請求であれ不当解雇事案であれ証拠がはっきりしていれば最初の1回の期日で終結することがある実情も考えれば、少額訴訟で安心して勝てるだけの証拠をもっている人なら労働審判を選んだほうがいいと筆者は考えています。
労働審判では残業代(時間外労働割増賃金)未払いに対する付加金の請求は通りませんが、この点は少額訴訟でも事実上同じです。裁判所は簡単には付加金給付判決を出しませんし、出したところで付加金など支払わずに済む方法はあります。付加金に着目して少額訴訟が有利だと考えるべきではありません。
少額訴訟に向かない案件
ここでは労働紛争労働側で、少額訴訟の利用に向かない案件や状況を考えてみます。
使用者側が労働者側に債権を持っている
具体的には損害賠償請求権や前借りしたお金・資格取得費用立替金などの請求を会社から労働者にすることが可能な状況です。
この場合でも賃金との相殺はできませんが、会社側からすれば少額訴訟で労働者側からの請求だけ迅速に認められては困ります。当然、被告側は通常訴訟への移行を考えますので少額訴訟の選択は不適です。
証拠がない・書類では存在しない典型的には、慰謝料請求
経営者や職制がウソをつきやすく、その排除が難しい状況です。
この場合は訴訟そのものが不適ではないか、という考え方もあるでしょう。安易な士業にもそう決めつける人がいます。
この場合、わかりやすい証拠がなくても労働者側の請求に関わる間接的な記録や痕跡をできるだけ集めて丁寧に説明し、相手の反論の不十分さや矛盾を突いていくことを期待して、複数回の期日が設定される通常訴訟を選んだほうがよいと考えます。
パワハラなどの慰謝料請求は少額訴訟を思いつく労働者に、利用は不適だと回答する典型的な案件です。
ハラスメントの事実があったことまでは証拠を出せても、「その事実があったから、その損害が発生した」という関係(因果関係)を証拠で示すことが難しいからです。
一部請求を試みる
これはだいたい、ダメな素人が思いつきます。
一部請求を考える人の多くは、単に60万円以下の請求なら1日で終わるという点にだけ注目しています。訴訟としての難易度については何も考えていないか、少額訴訟だから簡単だと根拠なく信じているだけです。
実際には相手のウソがうまければ一期日で敗北させられる危険がある一方、それに対処できるだけの証拠があるなら最初から請求全額で通常訴訟または労働審判を利用するほうが最終的な実費も少なくなるため、少額訴訟による一部請求には全くメリットが見いだせません。
もう一点、簡易裁判所の裁判官は事実関係の複雑な訴訟を嫌う(書類をよく読まず、審理が雑な)印象があり、勝ち負けの可能性を試してみたいから一部請求をしたい、という意向にも沿っていないと考えます。
仮に数百万円単位の請求権がある場合、一部請求でも140万円より多くして地方裁判所に訴えを起こしたほうがましな判断が出てくると筆者は考えます。
残業代請求の複雑なもの
ある手当が割増賃金に算入されるか否か・みなし残業代制度の当否・管理監督者への該当性・変形労働時間や裁量労働制の有効無効といった争点がある残業代請求は請求額が少なくても、少額訴訟に不適です。
これらは労働時間のほか、働き方の実情を丁寧に主張・立証する必要がありますので少額訴訟は当然不適であるほか、労働審判でも少し難しい面が出てきます。
場合によっては最初から、地方裁判所の通常訴訟を選ぶかもしれません。
当事務所では少額訴訟でも、訴状作成に十分な準備をします
『少額訴訟や、簡易裁判所の訴状の記載は簡単だ』ウェブにはそんな情報ばかりです。
たしかに制度上、それを目指してはいます。数十時間分のアルバイトの給料その他時給制の賃金体系を取る人の残業代を支払わせる程度の訴訟なら、裁判所に備え付けられている定型訴状に手書きした「紛争の要点」から裁判官が必要な事実を読みとってくれるでしょう。
ではこれを、請求額は少なくても月給制で複数の手当から残業代や平均賃金の計算を複雑に行うような訴訟でやったらどうなるでしょう?
特に残業代の請求を考えるかたは最近増えてきていますが、そうした方が名ばかり管理職あるいは労働時間制の例外(みなし労働時間制など)を適用されている可能性があるならどうでしょう?
裁判所か被告によって、通常訴訟へ移行させられるだけです。
事案が複雑だ、というのは少額訴訟を通常訴訟に移行させる理由として、まさに一般的です。
労働条件のいい加減な会社で、基本給の未払いに加えてサービス残業をさせられた末クビにされたような場合をみてみましょう。概して労働条件が悪いほど、適用される労働基準法の条文は多く裁判上の請求は複雑になってきます。
数ヶ月にわたって未払いの残業代があり、それも法定労働時間を上回る分・深夜労働・休日労働分と別れて存在し、その合計を出して、それをもとにさらに平均賃金を計算して解雇予告手当の支払い請求を併合する…そんな裁判で、事実の経過としての「紛争の要点」をだらだら書いたとしても、そこからいかなる適用法条でどんな主張をしたいかを、簡易裁判所の裁判官に正確に読みとってもらおうというのは、それが通常訴訟でも難しい注文です。
こうした、請求額は低くても主張として複雑になってしまう面がある労働紛争をあえて少額訴訟で迅速に解決することを目指すなら、訴状の記載を必要に応じて詳細にする必要があります。
少額訴訟という選択が適切かどうかも、法律相談を通じてよく考える必要があります。複雑でない労働紛争で迅速な判断を優先するなら、むしろ労働審判のほうが確実に三回の期日で結論を出してくれます。
またそれ以前に、労働法の知識がないために請求できる権利を見落とすようなことも、自分で訴訟を起こす場合にはあり得ます。上記の例なら残業代の計算を誤ったり遅延利息の請求を忘れたりする可能性です。
筆者は社会保険労務士として、労働基準法はじめ労働社会保険諸法令に精通しています。ですから訴状作成前の相談を入念に行って、適切に権利関係を整理したうえで訴状を作成し依頼人の権利を守ることができます。これは一般の司法書士事務所にない特色です。
訴状作成については作った書類の枚数と関係なく「依頼人が訴訟上請求する金額」の5%程度と「訴訟が終わって支払われることになった金額」の15%の合計を料金上限にする一方、作った訴状の枚数が少ないなど書類作成枚数によって料金を計算したほうが安いときには、そちらを料金としています。
このようにすることで、念入りに準備する結果書類の枚数を増やしても、それが費用に反映しないようになっています。
労働紛争以外の裁判事務や事案が複雑な場合などでは、料率を変更したり書類作成枚数によって料金を定めます