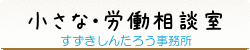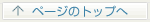労働契約とそれ以外の就労形態
質問
私は、
1.個人事業主であるとび職の手元として働いています。
2.日給1万5千円で調理師として働いています。調理師専門の業務請負会社からいまの派遣先に来ました。
3.一つのプロジェクトにつき5万円の約束でウェブサイトを作る在宅勤務をしています。
4.日給3万円で、ホステスとして働いています。
…使用者から突然、「明日から仕事をしなくていい」と言われたのですが、解雇予告手当を払って欲しいと言ったら「お前は労働者じゃないからそんなものは支払わない」と言われました。
一体どんな人が労働者にあたるのでしょう?
建前 実質をみて判断してください
ある人がある人(個人すなわち自然人や、会社などの法人)のために働く契約には、いろいろな形態があります。たとえば筆者がみなさんから相談を受ける場合には皆さんのためにその時間働いているわけですが、だからと言って皆さん方に雇われているわけではありませんね。このような専門職として知識や労力を提供する契約を委任契約といいます。
これに対して労働契約とはどんなものを言うのでしょう?
残念ながら、この要件を満たせば労働契約といえるわかりやすい手がかりはありません。
労働基準法(以下、労基法)の条文で「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下、「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とされています(労基法9条)。
事業というのは営利事業(つまり会社の活動)でも非営利事業(NPOや会社以外の法人の活動)でもかまいませんので、就労者が『使用される者』であるかどうかが問題になってきます。そして、何をもって事業に使用される者と判断するかはいくつかの基準が示されているだけです。
この点について、労働契約法の施行通達(平19.12.5厚労発基第1205001号)でも、
「労働者」に該当するか否かは、「労務提供の形態や報酬の労務対償性およびこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断される」、
「民法632条の「請負』、同法643条の『委任』又は非典型契約で労務を提供する者であっても、契約形式にとらわれず実態として使用従属関係が認められる場合」には、「労働者」に該当する
としています。
もう少し簡単になるように読み解くと、ある就労者が労働者であるか否かは、毎日の働き方の実情や報酬(通常は賃金)の決め方、関連するさまざまな要素を考慮して、少数の決め手に頼るのではなく総合的に判断しなければならない、ということです。さらに、名前や契約書だけ「請負契約」あるいは「委任契約」、その他よくあるのは「業務委託契約」など、名前だけが労働契約でない契約を結んで働く人についても、働き方や賃金の決め方の実情を見て使用従属関係があると認められる場合には、その就労者は労働者にあたり、契約の字面がどうあれ労働基準法をはじめとする労働法が適用される、ということになります。
労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)は、次のように示しており、この考え方は現在の裁判実務でも用いられています。
1「使用従属性」に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ仕事の依頼、従事業務の指示等に対する許諾の自由の有無
「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に関して許諾の自由を有していれば、指揮監督関係を否定する重要な要素になる。
これを拒否する自由を有しない場合は、一応、指揮監督関係を推認させる重要な要素となる。ただし、その場合には、その事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必要がある。
ロ業務遂行上の指揮監督の有無
a業務の内容および遂行方法に対する指揮命令の有無業務の内容および遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素である。しかし、通常注文主が行う程度の指示等にとどまる場合には、指揮監督を受けているとはいえない。
bその他
「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となる。
ハ拘束性の有無
勤務場所および勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には指揮監督関係の基本的な要素である。しかし業務の性質、安全を確保する必要等から必然的に勤務場所および勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。
二代替性の有無一指揮監督関係の判断を補強する要素
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていること、また、本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められていることなど、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつになる。
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
報酬が「賃金」であるか否かによって「使用従属性」を判断することはできないが、報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督のもとに一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、「使用従属性」を補
強することとなる。
2「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ機械、器具の負担関係
本人が所有する機械、器具が著しく高価な場合には自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」としての性格が強く、「労働者性」を弱める要素となる。
ロ報酬の額
報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に対して著しく高価である場合には、当該報酬は、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払いと認められ、その結果、「労働者性」を弱める要素となる。
ハその他
裁判例においては、業務遂行上の損害に対する責任を負う、独自の商号使用を認め
られている等の点を「事業者」としての性格を補強する要素としているものがある。
(2)専属性の程度
イ他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である場合には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に当該企業に従属していると考えられ、「労働者性」を補強する要素のひとつと考えて差し支えない。
ロ報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、「労働者性」を補強する要素のひとつと考えて差し支えない。
3その他
裁判例においては、?採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること、?報酬について給与所得として源泉徴収を行っていること、?労働保険の適用対象としていること、?服務規律を適用していること、?退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とするものがある。
本音 実質がどうあれ、その実質を立証できなきゃこっちの負けです
上記のとおりの基準でなんらかの判断がつけられるとして、労働者のあなたが使用者に「この就労形態によれば私と会社との契約は労働契約で、私は労働基準法が適用される労働者だ」などと言っても、簡単に使用者がその判断を受け入れるはずがありません。
ごくあたりまえのことですが、使用者側は労働者に労働法の保護を及ぼしたくないからこそ、あなたを労働契約以外の形態で就労させたいのです。就労者の労働者性を否定できることで使用者側は、厚生年金・健康保険など社会保険料の会社負担をはじめとして労働基準法所定の割増賃金や解雇予告手当などの支払を合法的に免れることができ、金銭的にたいへん大きなメリット(使用者側の言い方をすればまさにメリットですね)を得ることができるのです。こんなおいしい立場を、素人が内容証明を出してきた程度で軽々に手放すはずがありません。
では具体的にどうすれば、使用者側に労働者性を認めてもらえるのでしょう?
残念ながら労働基準監督署は積極的に事実を探索したり認定したりする機能は強くありません。期待しないほうがよいです。年金事務所(旧社会保険事務所)もそうですので、とにかく社会保険だけは加入したいという場合でも行政官庁経由でなんとかしてもらえるとは考えないでください。
合同労組への加入はどうでしょうか?そもそもあなたが労働者であるかどうか=つまり労働組合の構成員たり得るかが問題になってしまっているので、これも難しいと考えます。ただちに団体交渉が開かれるということにはならないでしょう。
そうすると、順当に残るのは裁判所における手続きになってしまいます。
具体的には、こちらの主張ではあくまで就労者と使用者の契約を労働契約だとしたうえで、所定の主張(たとえば、時間外労働割増賃金や解雇予告手当の請求)をおこなって通常訴訟なり労働審判を申し立てることになります。社会保険に過去に遡って加入したいとか、労働災害が発生している場合には、単に就労者が使用者に対して労働契約上の地位を有することの確認を求める訴訟・労働審判の申し立てもあり得るでしょう。
または、就労者側が自分が労働者だと信じて提訴した後になって使用者側から「原告労働者とは労働契約を交わしておらず、原告は業務委託契約によって労務を提供していたのだから、労働者ではない」という反論が出てきて一気に事態が複雑になる、ということもあります。
倫理的な観点を無視すれば、労働者が弁護士を代理人にせず自分で裁判手続きをはじめた場合(本人訴訟を起こした場合)に、真実がどうあれこうして大規模な反論をおこなって労働者を困惑させ、その状況下で会社側に都合のいい和解を求めるというのはなかなか悪くない作戦です。
なぜなら通常訴訟であれ労働審判であれ、裁判所での手続きに際しては労働者側で自分に有利な事実を証拠で明らかにする必要があります(立証責任といいます)。これは、各事業場における就労の実情を正確に把握したうえで裁判所に説明し、それを証拠で提出する、つまり主張と立証にわたる地道な努力を要することになり、訴訟としてある程度複雑になることはやむを得ません。ですのでこうした問題について、訴訟に関与しない社会保険労務士や労働関係に詳しくない司法書士に相談することはお勧めしませんし、弁護士でも市役所の無料法律相談などに配置されている人に相談して適切な回答が得られると期待すべきではありません。相談者が誰であれ、たとえば会社からのお金の支払いごとに給与明細をもらっていたという程度のかんたんな基準を示してパッと労働者性を判定するような奴に相談するのは危険で無駄です。ただしこのことは、『(職種が)●●の人には労働者でない人も多いからね』と言ったありふれた逃げ口上で相談を回避する間抜け相談担当者に一喜一憂する必要もないことを示しています。
最後に、この問題に労働者として対処したい場合、自分に有利な裁判例や事実をいくつか見つけただけで安心するような態度は絶対おすすめできません。むしろ自分に不利な要素をどれだけ発見でき、それに対処できるかが同じくらい重要な営みだと考えて、準備につとめてください。